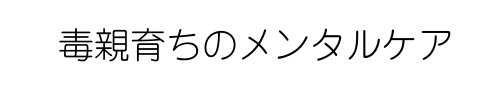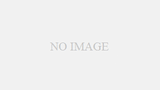私の母親は非常に情熱的で感情表現が豊かな人物です。そんな母の影響で、反面教師としてあまり感情を表に出さない私が育ったのかもしれません。彼女はユーモアのセンスにも長けていて、機嫌が良い時には、私たち家族も笑いが絶えない時間を過ごします。しかし、彼女は私が幼い頃、学校の成績や行事などに過剰に一喜一憂し、その重圧が私たちには時に負担となっていました。
特に印象に残っているのは、毎年行われていた持久走のことです。私は小学校3年生の時、9位という成績を収めたため、母の期待が大きくなったのを感じていました。4年生の持久走では、私は呼吸が苦しくなるのが嫌で、初めの2k程を遊び半分で適当に走った記憶があります。そして、後半ともなると、だんだん疲れて遅くなった級友達を追い抜いていき、学校の運動場に帰ってくる頃には、誰も前に走っていないことに気付きました。ふと私を呼ぶ声がし、気づくと母がしばらく並走した事を覚えています。その結果、意図せず1位になった私は、とっても嬉しい反面、なんだか面倒なことになったと感じました。それは、この出来事がきっかけで、母から毎回期待されるのが嫌だという気持ちがあったからです。
翌年の運動会の持久走では、わざと遅く走ったりして、こっぴどく母に叱られました。その時、私が何を感じていたのか正確には覚えていませんが、ただ「面倒なことに巻き込まれたくない」という感情が強かったと思います。期待されるということは、それだけプレッシャーがかかり、結果が出せなかった時には、また叱られたり、なじられたりする恐れがありました。こうした状況に対して、私は「努力することへの嫌悪感」を抱いていたのです。1位を取ったこと自体には一瞬の喜びを感じましたが、同時に「これが1位を取ることの感覚なのか」と、期待されることへの重圧を感じてしまい、それ以上の達成感を感じることはありませんでした。その時の私は、もうそれで満足してしまっていたのかもしれません。
なぜ私は目立つことを嫌ったのか
その時、目立つことへの嫌悪感がどこから来るのか、正確にはわかりませんが、今振り返るといくつかの心理的な要素が働いていたのだと思います。一つは、母親の過剰な期待によるプレッシャーです。母が期待することで、無意識に「目立つ=期待される=プレッシャーがかかる」と感じてしまい、それが嫌だったのかもしれません。また、目立つことが評価に直結し、評価されることが自分の価値の基準になることへの不安もあったと思います。その結果、「目立つ=負担」という思い込みが深層に刻まれていきました。
さらに、注目されることで不安定になることを避けるために、無意識のうちに目立たない方が安心だと感じていたのだと思います。目立つことで、評価や期待に応えなければならないというプレッシャーを感じるよりも、平穏を求めていたのかもしれません。
毒親育ちと過剰な期待の心理
ここで注目したいのは、毒親育ちという視点からの解釈です。毒親からの過剰な期待や評価は、しばしば子どもの自己価値感に深く影響を与えます。特に、親が過剰に一喜一憂する姿を見ることで、子どもは「注目される=評価される=期待に応えなければならない」というプレッシャーを感じるようになります。このような環境では、無意識に「目立たないこと」「期待されない方が楽」という思いが強くなり、目立つことが嫌いになるのです。
毒親育ちの子どもは、自己肯定感を外部の評価に依存しやすく、そのため目立って注目されることが「自分の価値を証明しなければならない」という無意識の重圧に繋がり、目立つことを避けるようになることが多いのです。このような心理は、無意識のうちに「目立たない方が安全」「期待されるとプレッシャーがかかる」という感覚を強化し、自己表現を抑制する結果につながります。
こうした経験から、目立つことが「面倒なこと」「期待されること」として脳裏に焼き付いてしまい、目立つのを避けるようになったのだと、今なら理解できます。
その頃の私は、何かにつけて一喜一憂されるのが嫌だと感じていました。そしていつの間にか、持久走で1位を取った面影もなく、私はただの「平均的な子ども」に戻っていきました。それは私の無意識が成せた心の『平穏』だったのです。